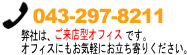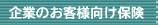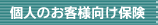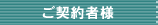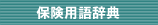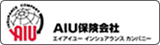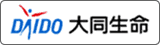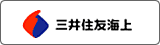- W.A.(だぶりゅ.えい.)
-
分損担保条件のこと。
貨物海上保険のてん補の範囲の基本的な条件の1つです。この条件では原則として分損は不担保ですが、例外として特定事故(分損担保条件)による損害については担保されます。 - 対人賠償保険(たいじんばいしょうほけん)
-
自動車の所有、使用または管理に起因して、他人の生命もしくは身体を害し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に支払われる保険です。
ただし、損害額が自賠責保険等による保険金を超過する場合に限り、その超過額のみを支払います。 - 大数の法則(たいすうのほうそく)
-
ある独立的に起こる事象について、それが大量に観察されればある事象の発生する確率が一定値に近づくという事であり、これを大数の法則といいます。
保険関係においては、個々人にとって偶発的な事故を大量に観察する事によって、ある確率でその発生率を全体として予測できるということになります。生命保険会社が保険料を決める際に使う年齢別・性別の死亡率・生存率は、「大数の法則」に基づいています。 - 対物賠償保険(たいぶつばいしょうほけん)
-
対物賠償保険とは、自動車の所有、使用または管理に起因して、他人の財物を滅失・破損もしくは汚損することにより、被保険者が相手の車や建物など物への賠償を対象とする保険です。ただし、自分や親族のものの損害には保険金は支払われません。保険金額は1事故ごとの最高支払限度額で定め、自動復元式が導入されています。
- 代理店(だいりてん)
-
生命保険募集代理店・損害保険代理店のこと。
損害保険代理店には保険契約の締結権がありますが、生命保険募集人は、その保険会社の為に生命保険契約の媒介をなすだけで、保険契約の締結権はありません。 - 代理店登録(だいりてんとうろく)
-
損害保険代理店は、財務省大臣宛てに登録申請書を提出し登録を受けなければ、保険契約の締結の代理を行う事ができません。
また、いったん登録を受けた者の違法行為に対しては、登録の取消・業務の停止等の行政処分が定められています。 - 代理店の種別(だいりてんのしゅべつ)
-
火災保険・自動車保険または傷害保険の委託を受けている損害保険代理店を、登録代理店単位に以下のの7基準によって、所属保険会社が、?日本損害保険協会の判定を得て、認定する分類。
(1)資格者状況
(2)業務遂行状況
(3)法令等遵守状況
(4)顧客対応状況
(5)管理体制状況
(6)挙績状況
(7)自己契約及び特定契約比率状況 - 他車運転危険担保特約(たしゃうんてんきけんたんぽとくやく)
-
他車運転危険担保特約とは、自動車保険の記名被保険者またはその配偶者が、他人の自動車(レンタカーや友人の車など)を運転中に起こした対人・対物賠償事故及び自損事故について、被保険自動車の契約内容と同一の担保を提供する特約で。
- 建物の構造級別(たてもののこうぞうきゅうべつ)
-
建物の構造級別とは、火災保険などで、料率表に定められた建物構造の優劣の区分のこと。建物の構造は、火災の燃焼危険や損傷危険の大きさなどが要素なので、その外壁・屋根・床・柱等により優劣を決め、この優劣の区分に従って適用料率が定められます。
- 他人の為にする保険契約(たにんのためにするほけんけいやく)
-
保険契約者が、自分の名において、自分以外の第3者を被保険者または保険金受取人として、締結する保険契約。
- 団体扱契約(だんたいあつかいけいやく)
-
団体扱契約とは、契約者が団体(会社・官公署等)に勤務し、その団体から給与の支払を受けている場合、団体が保険料を契約者の給与から差引いて保険者に支払う方式の契約のこです。
原則として、同一団体に一定数以上の契約者がいる場合に認められ、契約者に対しては、割増なしで保険料を12回または6回の分割払とする利便が与えられます。 - 団体生命保険(だんたいせいめいほけん)
-
生命保険でも、1つの契約で団体所属員全員が一括して低廉な保険料で加入できる保険のこと。原則として医的診査が行われません。所属員個人個人を危険選択の対象とせず、団体そのものを危険選択の単位としています。
団体保険ともいいます。 - 団体定期保険(だんたいていきほけん)
-
会社・工場・商店・官公庁・労働組合等の所属員を一括して契約する団体を対象とし、被用者の死亡保障を目的とした、通常保険期間1年の定期保険です。
保険料率は、平均料率が多く用いられ、税法上の特典として、事業主負担の保険料は損金処理、被保険者負担分は年末調整の対象となります。 - 団地保険(だんちほけん)
-
団地保険とは、団地やマンションに住んでいる人向けの火災保険の一種。
団地・マンションなどの耐火造共同住宅及びその収容動産について、住宅総合保険とほぼ同様の損害と費用のほか、修理費用・交通傷害・団地構内での傷害・賠償責任による損害を補償します。