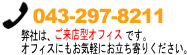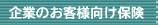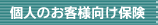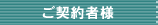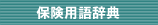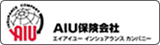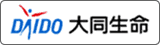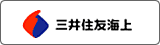- 債権保全火災保険(さいけんほぜんかさいほけん)
-
金融機関等の債権者は、債権の確実な回収を図る為に、債務者に対し建物などの不動産に抵当権を設定させますが、抵当権の目的物(抵当物)に火災などによって損害が生じた場合に、債権者が被る当該抵当債券の損害をてん補する保険。
- 再調達価額(さいちょうたつかかく)
-
保険契約の対象物(保険の目的)と同等の物を再取得または再購入する為に必要な額。
この再調達価額から経過年数や使用損耗による減価を差引いた額が時価(額)です。
損害保険では、時価を基準にして保険金を算出する保険が多いのですが、再調達価額を基準とする損害てん補方式を採る事によって、より完全な復旧を図る事が出来ます。 - 再保険(さいほけん)
-
保険経営の技術的基礎である大数の法則が働く為には同質の危険を多く集める必要があり、危険の平均化が十分に行われなければならない為に、保険会社がその保険契約に基づく保険金支払責任の全てあるいは一部分を別の保険会社に転稼する仕組みです。
- 再保険会社(さいほけんがいしゃ)
-
再保険会社とは、元受保険事業は行わず、もっぱら保険会社を相手に再保険を引受けることを専門とする再保険事業を行う会社。現在、東亜火災海上再保険株式会社と日本地震再保険株式会社の2社が営業しています。
- 再保険金(さいほけんきん)
-
保険会社の引受けた元受あるいは受再保険契約が再保険に付されている場合に、受再者が出再者に支払う保険金のことをいいます。
出再者が受再者から再保険金を受け取ることを「再保険金の回収」といいます。 - 再保険契約(さいほけんけいやく)
-
保険会社が保険契約によって引受けた責任(全部あるいは一部)を他の保険会社に付保する契約。
- 座席ベルト装着特別保険金(ざせきべるとそうちゃくとくべつほけんきん)
-
搭乗者傷害保険で、座席ベルト装着に対する優遇措置として支払われる保険金。
道路交通法にいう道路上で発生した事故で搭乗者が座席ベルトを装着していたにも関わらず死亡した場合に、通常の死亡保険金に加えて、搭乗者傷害保険金額の30%(300万円限度)相当額が特別保険金として支払われます。 - 査定(さてい)
-
生命保険において、生命保険会社が契約の締結にあたって、無条件で契約を承諾するか、諸種の条件を課するかを決定すること。保険加入申込者の申込書類・審査医からの報告書その他の資料に基づいておこなわれます。
査定は新契約時だけではなく、復活・保険種類の変更・死亡保険金支払の可否についても行われます。 - 残存保険金額(ざんぞんほけんきんがく)
-
残存保険金額とは,火災保険などにおいて、保険期間の中途で、保険者が一部損害(分損ともいう)の保険金を支払った場合、保険金額からその支払保険金を控除した残額をもって、損害発生日以後の保険期間に対する保険金額とする方式のことです。
- 算定会(さんていかい)
-
料率団体法に基づき設立された特殊法人のことで、保険事業の健全な発達を図り、保険契約者などの利益を保護する為に、公正な料率を算出する事などを目的としています。
主な事業は、保険料率の算出・大蔵大臣への認可申請・損害率及び危険の測定その他保険料率算出に関する必要な調査・研究及び資料の収集などです。